調整内容レポート その17 (ASP EBR Mod.0:中編)
Gnnsmithバトン基本調整内容レポート、ASP EBR Mod.0の中編をお届けいたします。(前編はこちら)


前編の最後でようやく裸になったメカボックスから、まずはモーターホルダーを取り外します。

モーターホルダー前部のピニオンギヤ付近には、汚れたグリスが生乾きのような状態でこびりついていました。これではメカボックス内部もさぞや汚れているだろうと思いつつ開いてみたところ・・・


想像していたほどではありませんでしたが、ご覧の通りとてもそのまま使うわけには行かない状態になっていました。

ベベルギヤを取り出してみれば、この有様です。このEBRは、作られたばかりの製品のはずなのですが、やはりまだまだ、中華エアガンを舐めてかかってはいけないようですね。



これら汚れを含んだ油分を、いつものように強力パーツクリーナーで入念に洗浄。ギヤの歯に入り込んだ油分をブラシで丁寧に落としつつ、ゆがみや欠損の有無を確認しています。上3枚の画像は、洗浄を終えたベベルギヤ、スパーギヤ、セクターギヤのアップです。中段のセクターギヤには、ずいぶん大きいセクターチップが付いていますね。


各種ギヤと同様、メカボックス内側にこびりついていた汚れもすべて洗い流します。チューナー陣によれば、メカボックスの仕様が変わって、仕上げがきれいになっているとのことでした。

軸受けは、いわゆるメタル軸受けが採用されています。しっかり圧入されていたため、ここでは取り外してからの接着固定は行っていません。

メカボックス内部の洗浄が完了したところで、まずはベベルギヤの位置を出して行きます。シムを入れてメカボックスを閉じ、モーターホルダーを取り付けて、ピニオンギヤとベベルギヤとのクリアランスを入念に調整。今回はこれがなかなか決まらず、担当チューナーは分解、組み立てをかなりの回数に渡って繰り返し、妥協の無いシム調整を行っていました。

ベベルギヤのシム調整が決まったところで、ギヤ用のグリスを塗付します。細筆を使って、すべての歯と歯の間にグリスを行き渡らせます。なお、メカボックスの造りはVer.7に準じていますが、これらのギヤはVer.2、Ver.3用のものが採用されているのは面白いところですね。

ベベルの位置が決まってしまえば、スパーとセクターのシム調整はスムーズに進みます。この後、メカボックスを閉じ、モーターホルダーを取り付けて、バッテリーを繋いで回した際のギヤノイズの有無を確認しましたが、目立つような異音は無く、静かに回転していました。この確認を持って、シム調整は完了です。

こちらはEBRに使用されている樹脂製ピストンです。ラックギヤ両側にリブの無い、いわゆるVer.7用の15枚歯ピストンです。ピストンに入っているスプリングは引っ張っても抜けないので、内側で固定されているのでしょうね。

こちらはシリンダーヘッドが付いた状態のシリンダーです。ご覧の通り加速シリンダーですが、ちょっと見たことがないような大きさのエア抜き穴が開いていますね。


シリンダーヘッドを前方から見ると、エアーノズルが上側に、かなり思い切ってオフセットされていました。

シリンダーヘッドの裏側(ピストン側)には、ご覧のような形のクッションラバーが貼り付けられています。クッションが空気の出口にかかるようなことの無いよう、丁寧に作られていますね。


給弾ノズルはシンプルな形状のもので、先端の穴の形状にも、特に工夫は施されていませんでした。

こちらはタペットプレートですが、ピストン同様、マルイVer.7用に準拠した設計になっています。形状と作動に問題は見られなかったため、特に加工等することなく、このまま使用します。

こちらはピストンヘッドを正面から写した画像ですが、5個の吸気穴に加え、中央にトルクスネジが使われているのがおわかりいただけるでしょうか。

このネジを外すと、ピストン内部に固定されていたウェイトが外れ、そこに噛み込む形ではまっていたスプリングも取り外すことが出来ました。

スプリングが外れたところで、ピストンヘッド中央のネジにネジロック剤を塗付して、ピストン先端にしっかり固定します。発射するたび強い衝撃にさらされる部分なので、ネジロック剤は必須ですね。

大きいエア抜き穴が開いた加速シリンダーは使わず、穴のないフルシリンダーに交換するのですが、この際ちょっとした問題が生じます。

もともと入っていたシリンダーは、エア抜き穴の後方、赤丸で囲んだ位置に、小さい切り欠きが設けられているのです。

これは、メカボックスの中でシリンダーの位置を固定するためのもので、黄色い丸で囲んだ部分にある突起と噛み合うようになっているわけですね。

フルシリンダーであれば特に向きを気にする必要は無く、この突起は不要なので、画像のようにリューターで削り落としました。


シリンダーヘッドから突き出したエアーノズルに、シリコングリスを薄く塗付し、給弾ノズルをはめ込みます。尚この固体は、シリンダーヘッドにシールテープを巻くといった気密漏れ対策は必要ありませんでした。

ピストンにもシリコングリスを丁寧に塗付します。作業工程のご紹介を省略してしまいましたが、ピストンラックギヤの最後の1枚は削り落としています。

グリスを塗ったピストンをシリンダーに挿し込み、タペットプレートを取り付けました。ここで、ノズル先端を指で押さえてピストンを押し込むエア漏れチェックを行いましたが、まったく問題はありませんでした。
といったところで、中編はここまでです。次回後編では、SBD(ショットキーバリアダイオード)の取り付けと、バレル、チャンバーまわりの調整から完成までを一気にご紹介いたします。




前編の最後でようやく裸になったメカボックスから、まずはモーターホルダーを取り外します。

モーターホルダー前部のピニオンギヤ付近には、汚れたグリスが生乾きのような状態でこびりついていました。これではメカボックス内部もさぞや汚れているだろうと思いつつ開いてみたところ・・・


想像していたほどではありませんでしたが、ご覧の通りとてもそのまま使うわけには行かない状態になっていました。

ベベルギヤを取り出してみれば、この有様です。このEBRは、作られたばかりの製品のはずなのですが、やはりまだまだ、中華エアガンを舐めてかかってはいけないようですね。



これら汚れを含んだ油分を、いつものように強力パーツクリーナーで入念に洗浄。ギヤの歯に入り込んだ油分をブラシで丁寧に落としつつ、ゆがみや欠損の有無を確認しています。上3枚の画像は、洗浄を終えたベベルギヤ、スパーギヤ、セクターギヤのアップです。中段のセクターギヤには、ずいぶん大きいセクターチップが付いていますね。


各種ギヤと同様、メカボックス内側にこびりついていた汚れもすべて洗い流します。チューナー陣によれば、メカボックスの仕様が変わって、仕上げがきれいになっているとのことでした。

軸受けは、いわゆるメタル軸受けが採用されています。しっかり圧入されていたため、ここでは取り外してからの接着固定は行っていません。

メカボックス内部の洗浄が完了したところで、まずはベベルギヤの位置を出して行きます。シムを入れてメカボックスを閉じ、モーターホルダーを取り付けて、ピニオンギヤとベベルギヤとのクリアランスを入念に調整。今回はこれがなかなか決まらず、担当チューナーは分解、組み立てをかなりの回数に渡って繰り返し、妥協の無いシム調整を行っていました。

ベベルギヤのシム調整が決まったところで、ギヤ用のグリスを塗付します。細筆を使って、すべての歯と歯の間にグリスを行き渡らせます。なお、メカボックスの造りはVer.7に準じていますが、これらのギヤはVer.2、Ver.3用のものが採用されているのは面白いところですね。

ベベルの位置が決まってしまえば、スパーとセクターのシム調整はスムーズに進みます。この後、メカボックスを閉じ、モーターホルダーを取り付けて、バッテリーを繋いで回した際のギヤノイズの有無を確認しましたが、目立つような異音は無く、静かに回転していました。この確認を持って、シム調整は完了です。

こちらはEBRに使用されている樹脂製ピストンです。ラックギヤ両側にリブの無い、いわゆるVer.7用の15枚歯ピストンです。ピストンに入っているスプリングは引っ張っても抜けないので、内側で固定されているのでしょうね。

こちらはシリンダーヘッドが付いた状態のシリンダーです。ご覧の通り加速シリンダーですが、ちょっと見たことがないような大きさのエア抜き穴が開いていますね。


シリンダーヘッドを前方から見ると、エアーノズルが上側に、かなり思い切ってオフセットされていました。

シリンダーヘッドの裏側(ピストン側)には、ご覧のような形のクッションラバーが貼り付けられています。クッションが空気の出口にかかるようなことの無いよう、丁寧に作られていますね。


給弾ノズルはシンプルな形状のもので、先端の穴の形状にも、特に工夫は施されていませんでした。

こちらはタペットプレートですが、ピストン同様、マルイVer.7用に準拠した設計になっています。形状と作動に問題は見られなかったため、特に加工等することなく、このまま使用します。

こちらはピストンヘッドを正面から写した画像ですが、5個の吸気穴に加え、中央にトルクスネジが使われているのがおわかりいただけるでしょうか。

このネジを外すと、ピストン内部に固定されていたウェイトが外れ、そこに噛み込む形ではまっていたスプリングも取り外すことが出来ました。

スプリングが外れたところで、ピストンヘッド中央のネジにネジロック剤を塗付して、ピストン先端にしっかり固定します。発射するたび強い衝撃にさらされる部分なので、ネジロック剤は必須ですね。

大きいエア抜き穴が開いた加速シリンダーは使わず、穴のないフルシリンダーに交換するのですが、この際ちょっとした問題が生じます。

もともと入っていたシリンダーは、エア抜き穴の後方、赤丸で囲んだ位置に、小さい切り欠きが設けられているのです。

これは、メカボックスの中でシリンダーの位置を固定するためのもので、黄色い丸で囲んだ部分にある突起と噛み合うようになっているわけですね。

フルシリンダーであれば特に向きを気にする必要は無く、この突起は不要なので、画像のようにリューターで削り落としました。


シリンダーヘッドから突き出したエアーノズルに、シリコングリスを薄く塗付し、給弾ノズルをはめ込みます。尚この固体は、シリンダーヘッドにシールテープを巻くといった気密漏れ対策は必要ありませんでした。

ピストンにもシリコングリスを丁寧に塗付します。作業工程のご紹介を省略してしまいましたが、ピストンラックギヤの最後の1枚は削り落としています。

グリスを塗ったピストンをシリンダーに挿し込み、タペットプレートを取り付けました。ここで、ノズル先端を指で押さえてピストンを押し込むエア漏れチェックを行いましたが、まったく問題はありませんでした。
といったところで、中編はここまでです。次回後編では、SBD(ショットキーバリアダイオード)の取り付けと、バレル、チャンバーまわりの調整から完成までを一気にご紹介いたします。
後編はこちら




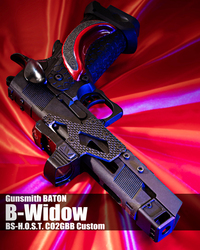

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)


















