調整内容レポート その16 (Magpul PTS PDW:後編)
Gunsmithバトン調整内容レポート『Magpul PTS製 PDR』【持ち込み】調整&チューン の後編をお届けいたします(前編はこちら)。
後編はメカボックス内部の調整からです。

まず、給排気系パーツから見ていきましょう。シリンダーはフルシリンダー、ピストンはポリカーボネート樹脂の透明なものです。このポリカピストンはより強度の高いBATON フルメタルティースピストンに交換です。

シリンダーはバレル長に対してフルシリンダーではエアの容量が過剰ですので加速シリンダーに換装します。


こちらはシリンダーヘッドなのですが、ご覧のとおりエアを放出する穴が中心からずれている特殊なものです。と、そんなことよりも穴の形状をよく見ていただきたいのですが、かなり大きなバリが残っているのがお分かりいただけると思います。このままではエアの通りを阻害してしまいますので、リューターでバリを処理しました。

次はピストンです。一度メカボックスに仮組みして動きを確認したところ、少々引っかかっている様な動きを見せましたので干渉している箇所を削ります。今回はピストンのレールの部分、そこの角を軽く削ってあげます。

削ったら再度動きを確認します。写真のようにドライバーでピストンを支え、上下に抵抗無くピストンがスムーズに動けばOKです。

ピストンの加工が済みましたら、適したピストンヘッドを装着します。ネジロックもちゃんと塗付しておきましょう。



組み上がったピストンに筆を用いて丁寧にグリスを塗っていきます。

シリンダーに対してシリンダーヘッドの入りが甘かったので、シールテープを巻き気密をしっかり確保します。

ノズルが被さる部分にもグリスを塗り、給排気系の調整は完了です。
続いて駆動系の調整に移りますが、その前に軸受けが少々緩かったのでしっかり固定させたいと思います。

使うのはコチラ、粘度が低いかなりサラッとした瞬間接着剤です。これを軸受けとメカボックス本体の隙間に流し込みます。

写真の通り、軸受けと本体の境界の部分にごく少量の接着剤を流すと毛細管現象により自然に染みこんでいきます。この際、ベアリングの部分に接着剤が流れてしまわないように注意して下さい。軸受けが使い物にならなくなってしまいます!

さて、準備が整いましたのでシムの調整に入りましょう。ギヤに付着していたグリスはパーツクリーナーでしっかり落としておきました。

先ずはベベルギヤとピニオンギヤのかみ合わせを調整します。先ずは写真で示している部分、ベベルギヤの歯の外周とピニオンギヤの歯の後端がぴったり一致する様にモーターの位置を合わせておきます。

ベベルのシムをある程度調整したところで、一度仮組みをしてべベルギヤとピニオンギヤのバックラッシュを確認します。写真の通りこのメカボックスはベベルギヤが入る箇所の付近に窓が空いており、バックラッシュの確認が非常にしやすくなっています。
確認の方法ですが、この窓からギヤを突いてみてどれ位動くのかを見ます。何度も開け閉めを繰り返し、ほんの僅かな動きの違いの差を感じ、適正なシムの組み合わせを探ります。

・・・と、ここで確認のために一度電源を繋いで回してみたのですがどうにもノイズが消えませんでした。音の出処からピニオンとベベルの部分からノイズが聞こえるようです。

そこでピニオンギヤをMODIFY-TECH製のピニオンギヤに交換してみたところ驚くぐらい静かに!ベベルとピニオンの相性でここまで変わるのかと感心してしまいました。
一度ベベルギヤが決まってしまえばスパー、セクターはそれに合わせて調整するだけです。

タペットプレートにも軽くグリスを塗布し、メカボックス内部の調整はこれで完了です。

さて、ここで勿論スイッチも組み込むわけなのですが、今回はFET装着のご依頼もありましたので装着しようと思います。

幸い、PDRはメカボックスの入る部分の前方FETを収めるのに十分なスペースがありますので、そこにFETが来るように配線を考えます。今回は写真の様な配線になりました。

最後にチャンバー周りの調整です。HOPアームの押し方がG36のものと似ていますね。


写真はの黒い小さなパーツは従来のチャンバーでいうところのHOPアームに当たる部分なのですが、このHOPアームに難点があります。それは本来押しゴムに当たる部分までもが、一体成型の硬い樹脂製で出来てしまっているということです。
ここが硬いとHOPを掛けた際のBB弾の抜けが悪くなり、初速が極端に落ちるという問題が発生してしまうのです。この個体も例に漏れず調整前はまともに弾が飛ばないレベルの初速でした・・・
そこで、このアームを従来品通りに押しゴムが使えるよう加工します。


加工自体は簡単で、アームの半円部分を切り飛ばし棒ヤスリで押しゴムが収まる様な窪みを削りだしてあげるだけです。と、やること自体は簡単なのですが、少しでもこの窪みの形がゆがむと弾道が乱れてしまう恐れがあり見た目以上に難易度の高い作業なのです。
しかし、この様な難しい加工も弊社チューナーの手にかかればあっという間にできてしまいます。写真の通り、綺麗に押しゴムが収まってるのがわかります。


パッキンはマルイ製のものに換装して組み上げます。

全て組み上げ弾速をチェック。初速は91~92m/sで安定しました。集弾性も30m先のターゲットをしっかり捉え、まともに飛ばなかった最初の状態が信じられない程です。
今回のように内部が綺麗で良く出来ている海外製電動ガン出会っても、本来秘めているポテンシャルを発揮するには様々な調整が必要であることがお分かりいただけたかと思います。
ものによっては箱出しでもある程度の性能を発揮してしまう銃があるのですが、調整次第では更に期待以上の性能に化けるものがあるかもしれません。気になった方は是非ともご依頼の検討をよろしくお願いします!



後編はメカボックス内部の調整からです。

まず、給排気系パーツから見ていきましょう。シリンダーはフルシリンダー、ピストンはポリカーボネート樹脂の透明なものです。このポリカピストンはより強度の高いBATON フルメタルティースピストンに交換です。

シリンダーはバレル長に対してフルシリンダーではエアの容量が過剰ですので加速シリンダーに換装します。


こちらはシリンダーヘッドなのですが、ご覧のとおりエアを放出する穴が中心からずれている特殊なものです。と、そんなことよりも穴の形状をよく見ていただきたいのですが、かなり大きなバリが残っているのがお分かりいただけると思います。このままではエアの通りを阻害してしまいますので、リューターでバリを処理しました。

次はピストンです。一度メカボックスに仮組みして動きを確認したところ、少々引っかかっている様な動きを見せましたので干渉している箇所を削ります。今回はピストンのレールの部分、そこの角を軽く削ってあげます。

削ったら再度動きを確認します。写真のようにドライバーでピストンを支え、上下に抵抗無くピストンがスムーズに動けばOKです。

ピストンの加工が済みましたら、適したピストンヘッドを装着します。ネジロックもちゃんと塗付しておきましょう。



組み上がったピストンに筆を用いて丁寧にグリスを塗っていきます。

シリンダーに対してシリンダーヘッドの入りが甘かったので、シールテープを巻き気密をしっかり確保します。

ノズルが被さる部分にもグリスを塗り、給排気系の調整は完了です。
続いて駆動系の調整に移りますが、その前に軸受けが少々緩かったのでしっかり固定させたいと思います。

使うのはコチラ、粘度が低いかなりサラッとした瞬間接着剤です。これを軸受けとメカボックス本体の隙間に流し込みます。

写真の通り、軸受けと本体の境界の部分にごく少量の接着剤を流すと毛細管現象により自然に染みこんでいきます。この際、ベアリングの部分に接着剤が流れてしまわないように注意して下さい。軸受けが使い物にならなくなってしまいます!

さて、準備が整いましたのでシムの調整に入りましょう。ギヤに付着していたグリスはパーツクリーナーでしっかり落としておきました。

先ずはベベルギヤとピニオンギヤのかみ合わせを調整します。先ずは写真で示している部分、ベベルギヤの歯の外周とピニオンギヤの歯の後端がぴったり一致する様にモーターの位置を合わせておきます。

ベベルのシムをある程度調整したところで、一度仮組みをしてべベルギヤとピニオンギヤのバックラッシュを確認します。写真の通りこのメカボックスはベベルギヤが入る箇所の付近に窓が空いており、バックラッシュの確認が非常にしやすくなっています。
確認の方法ですが、この窓からギヤを突いてみてどれ位動くのかを見ます。何度も開け閉めを繰り返し、ほんの僅かな動きの違いの差を感じ、適正なシムの組み合わせを探ります。

・・・と、ここで確認のために一度電源を繋いで回してみたのですがどうにもノイズが消えませんでした。音の出処からピニオンとベベルの部分からノイズが聞こえるようです。

そこでピニオンギヤをMODIFY-TECH製のピニオンギヤに交換してみたところ驚くぐらい静かに!ベベルとピニオンの相性でここまで変わるのかと感心してしまいました。
一度ベベルギヤが決まってしまえばスパー、セクターはそれに合わせて調整するだけです。

タペットプレートにも軽くグリスを塗布し、メカボックス内部の調整はこれで完了です。

さて、ここで勿論スイッチも組み込むわけなのですが、今回はFET装着のご依頼もありましたので装着しようと思います。

幸い、PDRはメカボックスの入る部分の前方FETを収めるのに十分なスペースがありますので、そこにFETが来るように配線を考えます。今回は写真の様な配線になりました。

最後にチャンバー周りの調整です。HOPアームの押し方がG36のものと似ていますね。


写真はの黒い小さなパーツは従来のチャンバーでいうところのHOPアームに当たる部分なのですが、このHOPアームに難点があります。それは本来押しゴムに当たる部分までもが、一体成型の硬い樹脂製で出来てしまっているということです。
ここが硬いとHOPを掛けた際のBB弾の抜けが悪くなり、初速が極端に落ちるという問題が発生してしまうのです。この個体も例に漏れず調整前はまともに弾が飛ばないレベルの初速でした・・・
そこで、このアームを従来品通りに押しゴムが使えるよう加工します。


加工自体は簡単で、アームの半円部分を切り飛ばし棒ヤスリで押しゴムが収まる様な窪みを削りだしてあげるだけです。と、やること自体は簡単なのですが、少しでもこの窪みの形がゆがむと弾道が乱れてしまう恐れがあり見た目以上に難易度の高い作業なのです。
しかし、この様な難しい加工も弊社チューナーの手にかかればあっという間にできてしまいます。写真の通り、綺麗に押しゴムが収まってるのがわかります。


パッキンはマルイ製のものに換装して組み上げます。

全て組み上げ弾速をチェック。初速は91~92m/sで安定しました。集弾性も30m先のターゲットをしっかり捉え、まともに飛ばなかった最初の状態が信じられない程です。
今回のように内部が綺麗で良く出来ている海外製電動ガン出会っても、本来秘めているポテンシャルを発揮するには様々な調整が必要であることがお分かりいただけたかと思います。
ものによっては箱出しでもある程度の性能を発揮してしまう銃があるのですが、調整次第では更に期待以上の性能に化けるものがあるかもしれません。気になった方は是非ともご依頼の検討をよろしくお願いします!
以上、調整内容レポートその16 PDR編でした。





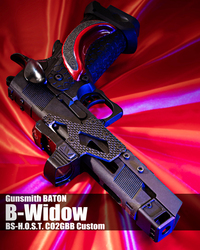

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)
















