調整内容レポート その12(RS ドラグノフSVD:中編)
Gunsmithバトン基本調整内容レポート、RS ドラグノフSVDの中編をお届けいたします。(前編はこちら)
※予約投稿の日時を間違えて、後編を先に公開してしまいました。大変申し訳ございませんが、昨日の記事が今回の中編に繋がりますので、前後関係を見なおしていただければ幸いです。

前回記事のラストで開いたメカボックス内部の、ギヤまわりを写してみました。ベベル→スパー→セクターと、3枚のギヤで構成されているのが一般激なメカボックスですが、ドラグノフの場合はメカボックスが前後に長いため、ベベルとスパーの間に、トランジッションギヤが1枚組み込まれています。また、このギヤが1枚増えたことで、セクターギヤの回転が逆になってしまうため、モーターに繋がる電源コードのプラスとマイナスが、逆に接続されるようになっている、つまり、モーターが逆回転するように作られているわけですね。

こちらはベベルギヤです。垂直に立った10枚の歯がトランジッションギヤと噛み合うと同時に、逆転防止ラッチを受け止める役割も果たしています。

こちらがRSドラグノフ独自採用のトランジッションギヤですね。ベベルギヤとスーパーギヤの中継役といったところでしょうか。

こちらはスパーギヤですが、一般的なスパーギヤとは少々違った形状になっていますね。


こちらのセクターギヤも、一般的なものより分厚い作りになっています。ピストンと噛み合う部分の歯数から、そのストロークの長さがわかりますね。

軸受けはベアリングタイプが採用されています。それぞれしっかりはまってていましたが、念のためすべて接着固定しました。メカボックス内部のグリスは、強力パーツクリーナーですべて洗い落としています。

ここからシム調整に着手です。ベベルギヤを入れたメカボックスにモーターホルダーを仮組みし、ベベルギヤとピニオンギヤの角度とクリアランスを確認して、ベベルギヤの下に入れるシムの厚みと枚数を決定。一旦メカボックスを閉じてモーターを回し、異常なギヤノイズが無いことを確認しました。


ベベルギヤの高さが決まったところで、ベアリング軸受けとベベルギヤにグリスを塗布してしまいます。

ベベルギヤの高さが決まってしまえば、残るギヤのシム調整はスムーズに進みます。トランジッションギヤが1枚増えていますが、やるべきことは特に変わりませんからね。画像は、シム調整を終えたギヤにグリスを塗って組み付けた状態です。

ピストンと噛み合うセクターギヤは、シム調整を決めた後、シリコングリスを塗布します。また、そのセクターギヤと接触する、スパーギヤの内側の歯にも、同様にシリコングリスを塗っています。

上記の工程を経て、すべてのギヤのシム調整とグリスアップが完了しました。この状態で一旦メカボックスを閉じ、モーターを組み付け、バッテリーを繋いで回しましたが、実にスムーズかつ、静かに動いていました。

こちらは逆転防止ラッチです。一般的なものと比べると、本体も軸もやや短めに作られているようですね。

シリンダーはメッキ仕上げの一般的なものに見えますが、実は・・・


東京マルイ製のフルシリンダーがすっぽり入ってしまうほど径が大きく、長く作られているのです。690mmにもなる長大なインナーバレルに対応するためには、これだけのシリンダーが必要だったのですね。

エアーノズルが中央下寄りに設けられたシリンダーヘッドは、シリンダーとのクリアランスが若干ルーズだったため、気密を確保するためにシールテープを巻き付けました。

給弾ノズルは長さ、形状ともに一般的なもので、先端のエアー吐出穴も、特に工夫の無い丸穴でした。セミオートオンリーのRSドラグノフですから、このままで何ら問題はありませんけどね。

樹脂製のピストンは、ビッグボア&ロングストロークに対応した、17枚歯という専用設計のものになっています。他社製品との互換は一切効かない上、補修パーツの入手も困難なので、大切に使いたいところですね。

大径のピストンヘッドも樹脂製で、吸排気穴の開いたタイプとなっています。

シリンダー内壁と、ピストンの必要な箇所にシリコングリスを塗布した後、給弾ノズルの先端を指で押さえてピストンを押し込み、気密を確認。問題ないことがわかったところで、メカボックス内側、ピストンとタペットプレートのはまるレールにグリスを塗布して、それぞれのパーツを組み付けます。
といったところで、中編はここまでです。 次回後編では、不動トラブルの原因解明と、バレル、チェンバーパッキンの調整。組み立て、完成までを一気にご紹介いたします。
※予約投稿の日時を間違えて、後編を先に公開してしまいました。大変申し訳ございませんが、昨日の記事が今回の中編に繋がりますので、前後関係を見なおしていただければ幸いです。

前回記事のラストで開いたメカボックス内部の、ギヤまわりを写してみました。ベベル→スパー→セクターと、3枚のギヤで構成されているのが一般激なメカボックスですが、ドラグノフの場合はメカボックスが前後に長いため、ベベルとスパーの間に、トランジッションギヤが1枚組み込まれています。また、このギヤが1枚増えたことで、セクターギヤの回転が逆になってしまうため、モーターに繋がる電源コードのプラスとマイナスが、逆に接続されるようになっている、つまり、モーターが逆回転するように作られているわけですね。

こちらはベベルギヤです。垂直に立った10枚の歯がトランジッションギヤと噛み合うと同時に、逆転防止ラッチを受け止める役割も果たしています。

こちらがRSドラグノフ独自採用のトランジッションギヤですね。ベベルギヤとスーパーギヤの中継役といったところでしょうか。

こちらはスパーギヤですが、一般的なスパーギヤとは少々違った形状になっていますね。


こちらのセクターギヤも、一般的なものより分厚い作りになっています。ピストンと噛み合う部分の歯数から、そのストロークの長さがわかりますね。

軸受けはベアリングタイプが採用されています。それぞれしっかりはまってていましたが、念のためすべて接着固定しました。メカボックス内部のグリスは、強力パーツクリーナーですべて洗い落としています。

ここからシム調整に着手です。ベベルギヤを入れたメカボックスにモーターホルダーを仮組みし、ベベルギヤとピニオンギヤの角度とクリアランスを確認して、ベベルギヤの下に入れるシムの厚みと枚数を決定。一旦メカボックスを閉じてモーターを回し、異常なギヤノイズが無いことを確認しました。


ベベルギヤの高さが決まったところで、ベアリング軸受けとベベルギヤにグリスを塗布してしまいます。

ベベルギヤの高さが決まってしまえば、残るギヤのシム調整はスムーズに進みます。トランジッションギヤが1枚増えていますが、やるべきことは特に変わりませんからね。画像は、シム調整を終えたギヤにグリスを塗って組み付けた状態です。

ピストンと噛み合うセクターギヤは、シム調整を決めた後、シリコングリスを塗布します。また、そのセクターギヤと接触する、スパーギヤの内側の歯にも、同様にシリコングリスを塗っています。

上記の工程を経て、すべてのギヤのシム調整とグリスアップが完了しました。この状態で一旦メカボックスを閉じ、モーターを組み付け、バッテリーを繋いで回しましたが、実にスムーズかつ、静かに動いていました。

こちらは逆転防止ラッチです。一般的なものと比べると、本体も軸もやや短めに作られているようですね。

シリンダーはメッキ仕上げの一般的なものに見えますが、実は・・・


東京マルイ製のフルシリンダーがすっぽり入ってしまうほど径が大きく、長く作られているのです。690mmにもなる長大なインナーバレルに対応するためには、これだけのシリンダーが必要だったのですね。

エアーノズルが中央下寄りに設けられたシリンダーヘッドは、シリンダーとのクリアランスが若干ルーズだったため、気密を確保するためにシールテープを巻き付けました。

給弾ノズルは長さ、形状ともに一般的なもので、先端のエアー吐出穴も、特に工夫の無い丸穴でした。セミオートオンリーのRSドラグノフですから、このままで何ら問題はありませんけどね。

樹脂製のピストンは、ビッグボア&ロングストロークに対応した、17枚歯という専用設計のものになっています。他社製品との互換は一切効かない上、補修パーツの入手も困難なので、大切に使いたいところですね。

大径のピストンヘッドも樹脂製で、吸排気穴の開いたタイプとなっています。

シリンダー内壁と、ピストンの必要な箇所にシリコングリスを塗布した後、給弾ノズルの先端を指で押さえてピストンを押し込み、気密を確認。問題ないことがわかったところで、メカボックス内側、ピストンとタペットプレートのはまるレールにグリスを塗布して、それぞれのパーツを組み付けます。
といったところで、中編はここまでです。 次回後編では、不動トラブルの原因解明と、バレル、チェンバーパッキンの調整。組み立て、完成までを一気にご紹介いたします。


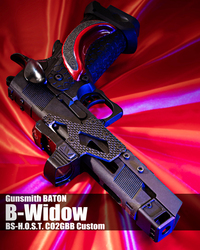

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)


















