調整内容レポート その6(CYMA MP5SD6(ブローバック):前編)
今回のGnnsmithバトン基本調整内容レポートは、SMGタイプ電動ガン中、永遠の定番とも言える、CYMA MP5SD6(ブローバック):についての内容をお届けします。

フルメタルボディに、ボルトカバーが動く擬似ブローバック機構を搭載したMP5SD6。CYMAといえば、老舗の本中華メーカーですが、箱出し状態の中身はどのようになっているのか、まずは初速を計測してみました。

1発目は55m/s程度の数値。ただ、中華電動ガンの場合は何発か撃つうちに当たりが取れるのか、初速が安定する場合がありますので、引き続き撃ってみますと・・・

なんど今度は、45m/s前後まで落ち込んでしまいました。この後も撃つ度に初速が下がり、30m/sという数値を確認したところでチェックは終了。まるでお話しにならないことがわかりましたので、弾道チェックは行わず、分解調整にとりかかることにしました。

ピンを2本抜くことでストックが外れ、レシーバーを上下に分解することが出来ます。このあたりの構造は実銃をきちんと再現していて好感が持てますね。

グリップフレーム後方にあるネジを外し、擬似ブローバックユニットをメカボックスから分離します。

分離した状態がこちらですね。メカボックスの後ろにコネクターが見えていますが、これはアッパーレシーバー後端から伸びたコネクターと接続し、ハンドガード内部のバッテリーコネクターへと繋がるものです。

画像中央、擬似ブローバックユニットの下面にある突起ですが、この部分が前後に動くピストンに引っかかることで、ボルトカバーがガチャガチャと動くギミックが実現しているわけですね。

グリップ内部から取り出したモーターは、かなり強力な磁力を発生していました。スチール製の作業机のフレームにくっついたら、相当な力でひっぱらないと外れませんでしたからね~。

次にロアーレシーバー左側面のセレクターレバーの下にあるイモネジを外し、セレクターレバー本体を引き抜きます。ここまでの作業で、ロアーレシーバーからメカボックスを取り出すことが出来ます。

取り出したメカボックスがこちら。黒く塗装された、一般的な形状のVer.2メカボックスですが、セレクタープレートが独特な形をしているのがおわかりいただけると思います。

その黒いメカボックスをパカっと開いてビックリ仰天。何年使い込んだらこうなるんだと、新品であることを疑いたくなるような汚れ具合だったのですよ。

こちらは右側メカボックスの内部ですが、ピストンレールの周囲に何かがびっしりと付着していますよね。これ、細かい金属粉がグリスの油分でこびりついたものなんですが、何をどうやったらこんな汚れ方をするのか、ちょっと見当がつきませんよね。

ギヤまわりにはご覧の通り、緑色のグリスと思われる粘液がこってりと充填されていました。軸受けがメカボックスから、ほとんどの抵抗無しに抜け落ちてしまったのも問題ですね。

メカボックスから取り出したギヤもご覧の通り、素手で触るのをためらうような状態でした。上でも書きましたが、軸受けがすっぽ抜けてギヤにくっついて着ちゃってます。

そして最大のサプライズがこちら。タペットプレートの前に、オレンジ色の破片が挟まっていました。こう書くと、何らかのトラブルで挟まったように思えますが、これは日本への輸出に当たり、初速を手っ取り早く下げるための手段として、中華エアガンに良く採用されている手法なのです。なるほど、これではまともな初速が出る道理がありませんよね。

取り出した破片のアップですが、おそらくはマズルキャップをカッター等で切り刻んだ代物でしょうね。私デイヴはこの有り様に驚いたのですが、担当チューナーによれば、「取ればいいだけだから、楽な方」とのことでした。

こちらは取り出したピストンを洗浄したものです。カーキっぽい成型色の、一般的な形状をしたピストンに見えますね。

吸排気穴の開いたピストンヘッドは、前面からネジ止めするタイプになっていました。一段引っ込んでいるとはいえ、ネジがむき出しになっているのが大胆ですよね。

こちらはピストンの内側を後方から撮った画像ですが、マルイさんの純正ピストンのように、ウェイトが内蔵されているのを写したものです。このウェイトがカラーの役目も果たすため、若干弱めのスプリングでも充分な初速が出せるとのことでした。

ピストンの上面後半部が、通常とは変わった形状になっているのがおわかりいだだけるでしょうか。この部分に設けられた突起が、上述した擬似ブローバックユニット下面の突起と噛み合って、ボルトカバーが動作するギミックを実現しているわけです。

こちらのピストン、15枚歯で作られていました。このままではピストンクラッシュ、いわゆるピスクラを引き起こす可能性が高いので・・・


最後の1枚をリューターで削り落としました。これで安心して組み込めるわけです。

ここでメカボックス内部を洗浄します。不気味な緑グリスをウェスで拭き取り、強力パーツクリーナーをたっぷり吹き付けて・・・

ブラシで隅々まで油分を書き出し、さらにパーツクリーナーで洗い流して、徹底的に洗浄します。

洗浄を終えたメカボックスの内部がこちら。付着していた油分は完全に除去しました。


同様にギヤも洗浄するのですが、ベベルギヤに付着した油分を落としていたところ、歯の谷間から小さい金属片が見つかりました。

ご覧の通り、欠落したスパーギヤの歯だったのですね。過去記事にも書きましたが、ギヤを洗浄する際に歯の欠けやゆがみをチェックするのは、こういうケースがあるためなのです。

言うまでもなく、歯の欠けたギヤでは使い物になりませんので、APS製のスパーギヤに交換して組み込みを進めて行きます。
といったところで、前編終了とさせていただきます。品質が向上したと言われる中華電動ガンですが、こういった個体もまだまだ存在しているので、油断は出来ませんよね。
次回後編では、シム調整から完成までの工程をご紹介いたします。

フルメタルボディに、ボルトカバーが動く擬似ブローバック機構を搭載したMP5SD6。CYMAといえば、老舗の本中華メーカーですが、箱出し状態の中身はどのようになっているのか、まずは初速を計測してみました。

1発目は55m/s程度の数値。ただ、中華電動ガンの場合は何発か撃つうちに当たりが取れるのか、初速が安定する場合がありますので、引き続き撃ってみますと・・・

なんど今度は、45m/s前後まで落ち込んでしまいました。この後も撃つ度に初速が下がり、30m/sという数値を確認したところでチェックは終了。まるでお話しにならないことがわかりましたので、弾道チェックは行わず、分解調整にとりかかることにしました。

ピンを2本抜くことでストックが外れ、レシーバーを上下に分解することが出来ます。このあたりの構造は実銃をきちんと再現していて好感が持てますね。

グリップフレーム後方にあるネジを外し、擬似ブローバックユニットをメカボックスから分離します。

分離した状態がこちらですね。メカボックスの後ろにコネクターが見えていますが、これはアッパーレシーバー後端から伸びたコネクターと接続し、ハンドガード内部のバッテリーコネクターへと繋がるものです。

画像中央、擬似ブローバックユニットの下面にある突起ですが、この部分が前後に動くピストンに引っかかることで、ボルトカバーがガチャガチャと動くギミックが実現しているわけですね。

グリップ内部から取り出したモーターは、かなり強力な磁力を発生していました。スチール製の作業机のフレームにくっついたら、相当な力でひっぱらないと外れませんでしたからね~。

次にロアーレシーバー左側面のセレクターレバーの下にあるイモネジを外し、セレクターレバー本体を引き抜きます。ここまでの作業で、ロアーレシーバーからメカボックスを取り出すことが出来ます。

取り出したメカボックスがこちら。黒く塗装された、一般的な形状のVer.2メカボックスですが、セレクタープレートが独特な形をしているのがおわかりいただけると思います。

その黒いメカボックスをパカっと開いてビックリ仰天。何年使い込んだらこうなるんだと、新品であることを疑いたくなるような汚れ具合だったのですよ。

こちらは右側メカボックスの内部ですが、ピストンレールの周囲に何かがびっしりと付着していますよね。これ、細かい金属粉がグリスの油分でこびりついたものなんですが、何をどうやったらこんな汚れ方をするのか、ちょっと見当がつきませんよね。

ギヤまわりにはご覧の通り、緑色のグリスと思われる粘液がこってりと充填されていました。軸受けがメカボックスから、ほとんどの抵抗無しに抜け落ちてしまったのも問題ですね。

メカボックスから取り出したギヤもご覧の通り、素手で触るのをためらうような状態でした。上でも書きましたが、軸受けがすっぽ抜けてギヤにくっついて着ちゃってます。

そして最大のサプライズがこちら。タペットプレートの前に、オレンジ色の破片が挟まっていました。こう書くと、何らかのトラブルで挟まったように思えますが、これは日本への輸出に当たり、初速を手っ取り早く下げるための手段として、中華エアガンに良く採用されている手法なのです。なるほど、これではまともな初速が出る道理がありませんよね。

取り出した破片のアップですが、おそらくはマズルキャップをカッター等で切り刻んだ代物でしょうね。私デイヴはこの有り様に驚いたのですが、担当チューナーによれば、「取ればいいだけだから、楽な方」とのことでした。

こちらは取り出したピストンを洗浄したものです。カーキっぽい成型色の、一般的な形状をしたピストンに見えますね。

吸排気穴の開いたピストンヘッドは、前面からネジ止めするタイプになっていました。一段引っ込んでいるとはいえ、ネジがむき出しになっているのが大胆ですよね。

こちらはピストンの内側を後方から撮った画像ですが、マルイさんの純正ピストンのように、ウェイトが内蔵されているのを写したものです。このウェイトがカラーの役目も果たすため、若干弱めのスプリングでも充分な初速が出せるとのことでした。

ピストンの上面後半部が、通常とは変わった形状になっているのがおわかりいだだけるでしょうか。この部分に設けられた突起が、上述した擬似ブローバックユニット下面の突起と噛み合って、ボルトカバーが動作するギミックを実現しているわけです。

こちらのピストン、15枚歯で作られていました。このままではピストンクラッシュ、いわゆるピスクラを引き起こす可能性が高いので・・・


最後の1枚をリューターで削り落としました。これで安心して組み込めるわけです。

ここでメカボックス内部を洗浄します。不気味な緑グリスをウェスで拭き取り、強力パーツクリーナーをたっぷり吹き付けて・・・

ブラシで隅々まで油分を書き出し、さらにパーツクリーナーで洗い流して、徹底的に洗浄します。

洗浄を終えたメカボックスの内部がこちら。付着していた油分は完全に除去しました。


同様にギヤも洗浄するのですが、ベベルギヤに付着した油分を落としていたところ、歯の谷間から小さい金属片が見つかりました。

ご覧の通り、欠落したスパーギヤの歯だったのですね。過去記事にも書きましたが、ギヤを洗浄する際に歯の欠けやゆがみをチェックするのは、こういうケースがあるためなのです。

言うまでもなく、歯の欠けたギヤでは使い物になりませんので、APS製のスパーギヤに交換して組み込みを進めて行きます。
といったところで、前編終了とさせていただきます。品質が向上したと言われる中華電動ガンですが、こういった個体もまだまだ存在しているので、油断は出来ませんよね。
次回後編では、シム調整から完成までの工程をご紹介いたします。


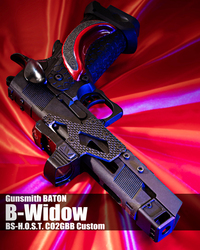

![[ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について [ Gunsmith BATON ] 持ち込み調整&チューンの内容について](http://img01.militaryblog.jp/usr/g/u/n/gunsmithbaton/IMG_3490a-s.jpg)


















